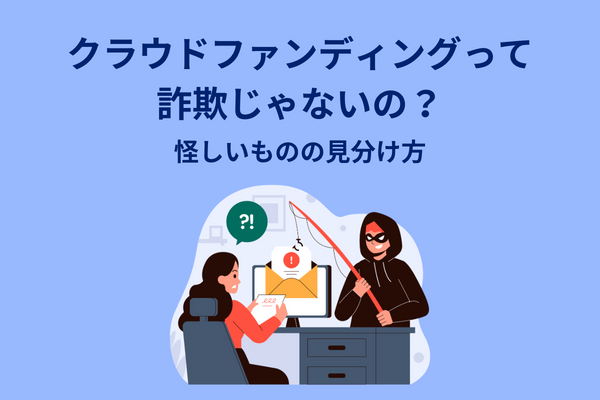
そもそもクラウドファンディングとは
クラウドファンディングとは、「こんなアイテムやサービスをつくりたい」「被災地の人々や保護動物を支援したい」といったプロジェクトを実現するために、Webを使って個人から広く支援金を募る方法です。
例えば「とにかく薄い財布を作りたい」というプロジェクトがあったとしましょう。このプロジェクトに支援をすると見返りとして完成した財布が届く、というイメージで、ちょっと変わったインターネット通販として使う人も多いです。これを「購入型クラウドファンディング」と呼びます。
「被災地支援」や「保護動物を助けたい」といったプロジェクトは、寄付型と呼ばれるクラウドファンディングになることが多いです。
購入型と異なり、寄付型には経済的価値のある見返りはありません。代わりに、「活動報告」や「主催者のWebページへの名前の掲載」といった、精神的な満足感を得られる見返りがあります。
ある程度のリスクは避けられない
そもそも、クラウドファンディング自体は怪しいものでも、まして詐欺のためのものでもありません。しかし、クラウドファンディングの仕組みを悪用した詐欺があるのも事実です。
そもそもクラウドファンディングには「投資」の側面があります。支援者はプロジェクトに魅力を感じ、それを応援したいと思ったからこそ、お金を支援してくれます。これはプロジェクトを実現させるための投資であり、投資である以上、リスクはゼロではありません。
ただ、「お金を持ち逃げするつもりでウソのプロジェクトを掲載する」「最初は詐欺を働くつもりはなかったが、お金が集まるのを見て魔が差した」という事例もあります。このようなものはプロジェクトの失敗ではなく、紛れもない詐欺です。
クラウドファンディング詐欺の手口
クラウドファンディングには失敗や詐欺のリスクもありますが、プロジェクトに支援したいという気持ちは、純粋なものなはず。できれば疑いの気持ちを持たず、気分よく支援したいものです。
詐欺を見抜き、本当に助けを必要としているプロジェクトを支援するためにも、まずはどんな詐欺の手口があるのか確認しておきましょう。
【クラウドファンディング詐欺の手口】
・リターンが紹介されていたものと違う
・リターンが届かず、連絡もつかない
・プロジェクトがいきなり中止される
・そもそもプロジェクト自体がウソ
リターンが紹介されていたものと違う
特に購入型クラウドファンディングでよくある詐欺の手口が、「リターンが紹介されていたものと違う」です。プロジェクトに掲載していたものと素材や品質が違っていたり、写真と異なるものが送られてきたり、さまざまな詐欺があります。
例えば「本皮の財布が届くはずだったのに合皮の財布が届く」という場合を考えてみましょう。合皮は本皮よりも安く、その差額分、詐欺師はお金を騙し取っています。最近は本皮にしか見えないような素材もあるので、素材が劣化してくるまで、なかなか気付けないでしょう。
リターンが届かず、連絡もつかない
対応のしようがなく困ってしまう詐欺の手口として、「リターンが届かず、連絡もつかなくなる」が挙げられます。購入型では商品やサービスが、寄付型では主に活動報告が、リターンとして提供されます。これらが届かないばかりか、問い合わせをしても連絡が来ないようなケースです。
予定されていた発送時期から1ヵ月経ってもリターンも連絡も届かず、特にアナウンスもないなら、詐欺を疑った方がいいでしょう。
プロジェクトがいきなり中止される
善意の支援者を特に戸惑わせる詐欺の手口が、「プロジェクトを中止してお金を持ち逃げする」かもしれません。
目標額に届きそう、あるいは少し超えた段階で、起案者(発案者)がいきなり「やっぱりこのプロジェクトは上手くいかないと思います」などと言い、プロジェクトを中止してしまいます。集まった支援金が起案者の手に渡っている場合、そのまま持ち逃げできてしまいます。
そもそもプロジェクト自体がウソ
クラウドファンディング詐欺には「集まった大金を見て魔が差してしまった」というケースもあります。しかし、弁明のしようもないのが「そもそもプロジェクト自体がウソ」なケースです。
要は、はじめからお金を騙し取るつもりで、人の善意を利用しているケースです。例えばすでに亡くなっている飼い犬を生きているように見せ、「治療費を集めたいです」と、約185万円を騙し取ろうとした事件があります(振込み前に発覚したため、未遂に終わりました)。
プロジェクト開始前に犬は亡くなっていて、それまでにかかった治療費を取り戻したいと思ったと犯人は供述していますが、それならそう書けばいいのです。
このようなケースは見抜くのが難しく、詐欺が発覚したのも偶然でした。掲載写真や文章をよく見て、あやふやな点や怪しい箇所がないか、よくチェックしましょう。
参考:クラウドファンディングの募金詐欺に注意! 死んだ飼い犬の治療費を取り返そうとして捕まった犯人の手口 │ INTERNET Watch
クラウドファンディング詐欺の見分け方
クラウドファンディング詐欺は、人の善意を踏みにじる許しがたい犯罪です。ただ、クラウドファンディング自体は怪しいものではなく、むしろ誰もが自分のやりたいことができる、より良い社会をつくるためのサービスとして登場しました。
詐欺もあるのは事実ですが、たいていのプロジェクトは社会や生活をより良くするための、すばらしいアイデアです。
必要としている人たちに支援を届けるためにも、クラウドファンディング詐欺を見分ける方法を頭に入れておきましょう。
【クラウドファンディング詐欺の見分け方】
・起案者についてしっかり調べる
・ページの内容や写真は要チェック
・目標額が高すぎるや低すぎるものは要注意
起案者についてしっかり調べる
クラウドファンディング詐欺を見抜くために、まずは起案者についてしっかり調べましょう。起案者が企業や団体なら、それは本当に存在する組織なのか。会社所在地に実在する住所で、代表者はどんな人なのかを調べるのです。
インターネット、特にSNSで、その組織のメンバーについての情報を集めるのもいいでしょう。
ページの内容や写真は要チェック
プロジェクトの内容や掲載されている写真は、詐欺を見抜くうえで重要な手がかりとなります。しっかりチェックしましょう。
お金を騙し取るつもりの、ウソのプロジェクトには、どこかあやふやな点があるものです。特に写真がフリー素材やどこかのWebサイトから無断転用しているものなら、怪しいと思った方がいいかもしれません。
先ほどの「すでに亡くなった飼い犬を生きているように見せ、治療費を騙し取ろうとしたケース」なら、最新の治療費明細を見せてもらうのもいいでしょう。このような書類が偽造されたものである可能性はゼロではありませんが、手がかりになるはずです。
目標額が高すぎるものや低すぎるものは要注意
プロジェクトの内容に対し、目標額の高すぎるものや低すぎるものは詐欺かもしれません。はじめからお金を騙し取るつもりなら、できるだけ高い金額を設定したくなるものです。
低すぎる場合は、支援金が目標額に届かず、お金を受け取れなくなることを危惧しているのかもしれません(クラウドファンディングには、設定した目標額に1円でも届かないと、集まった資金を受け取れないものがあります)。
「このプロジェクトに、こんなにお金がかかるのか?」「この金額で、こんなに大きなことができるのか?」と思ったら、詐欺を疑った方がいいかもしれません。似たようなプロジェクトを探し、必要額の相場を調べてみるのもいいでしょう。
【3ステップ】クラウドファンディング詐欺に遭ったときの対処法
クラウドファンディング詐欺に遭ったときの対処法と、それぞれをどんな流れで進めていけばいいのかを解説します。時間が経つほど状況は悪くなっていくはずですから、できれば記事を読みながら、すぐに取り掛かってください。
【クラウドファンディング詐欺に遭ったときの対処法】
STEP1.まずは証拠を集めよう
STEP2.クラウドファンディング会社に相談しよう
STEP3.消費者生活センターに相談しよう
STEP1.まずは証拠を集めよう
クラウドファンディング詐欺に遭ったと思ったら、まずは証拠を集めましょう。怪しいと感じているだけの段階でも、証拠を早めに集めておけば、すぐに次のステップに移れます。証拠とは、次のようなものです。
・プロジェクトページに掲載されたテキストや写真
・リターンの発送時期
・あるならメッセージのやりとり
メッセージのやりとりがないなら、疑問に感じている点を文章に起こして、起案者に問い合わせてみましょう。
例えばいつまで経ってもリターンが届かないなら、「4月に届くはずのリターンが未だに届かないのですが、すでに発送はされていますか? 送り先住所の間違いがあるといけないので、送り状の住所があれば知りたいです」のような問い合わせを送ってみましょう。
連絡が返ってこなかったとしても、メッセージを何通か送ることで、「連絡が取れないこと」を証明できます。
STEP2.クラウドファンディング会社に相談しよう
詐欺の証拠を集めたら、次はクラウドファンディング会社に相談をしてみましょう。リターンがいつまで経っても届かないことや、連絡すら返ってこないことを伝えれば、対応してくれるでしょう。
起案者も、1人の支援者からの連絡は無視できても、クラウドファンディング会社の連絡には返事をするかもしれません。
ただ、クラウドファンディング会社も「自社のサービスを悪用された」という意味では被害者であり、できることには限界があります。これで上手くいかないなら、次のステップに進みましょう。
STEP3.消費者生活センターに相談しよう
クラウドファンディング会社に相談しても事態が解決しないなら、消費者生活センターに相談するといいでしょう。
消費者生活センターとは、消費者と販売者とのトラブルを解決するための機関で、詐欺や悪徳商法への相談が全国から集まっています。情報力という意味では、クラウドファンディング会社よりも頼りになるかもしれません。
弁護士に相談したり警察に通報したりといった、その後の具体的なアドバイスももらえるはずです。弁護士に相談する場合、まずは地域の無料相談窓口を使ってみるといいでしょう。「〇〇市 無料の法律相談」と検索すると、予約を取るための電話番号が見つかるはずです。
リスクはあるが、ADRを利用するのもアリ
消費者生活センターに相談した後、ADRを利用するのもいいでしょう。ADRとは、消費者生活センターによる「消費者と事業者の紛争を解決するための手続き」です。利用料がかからず、これにより「仲裁」を受ければ、裁判と同じ効力を持つ解決方法を提示してもらうこともできます。
ただ、仲裁を受ける場合はその結果に従わなければならず、その後に同じ案件で裁判を受けることもできなくなります。仲裁の結果が不満でも不服申し立てはできないので、それなりのリスクがあります。やはりまずは、地域の無料法律窓口を相談するのがいいでしょう。
クラウドファンディングに支援する前に、情報を集めよう
クラウドファンディングとは本来、新しいアイデアを思いついたり社会的な意義のある取り組みをしたいと思ったりした人が、そのための資金を集めるためのものです。その仕組みが悪用され、詐欺事件が起こることもありますが、クラウドファンディング自体は怪しいものではありません。
クラウドファンディングに支援する前に、まずは起案者のことや、似たようなプロジェクトについての情報を集めましょう。情報が多いほど、怪しいプロジェクトだと見抜ける可能性が高くなります。
本記事で紹介したような詐欺は、支援者だけでなく、プロジェクトの起案者にとっても迷惑なものです。自分はきちんとした気持ちでやっているのに、ごく一部の詐欺師のせいで、自分のプロジェクトまで怪しく見えてしまうかもしれません。
自分の想いが伝わるプロジェクトページをつくる自信のない方は、クラウドファンディングサイト「OHACO」までぜひお問い合わせください。
OHACOではプロジェクトの内容を丁寧にヒアリングし、その魅力を伝える個別記事をつくっています。マーケティングや集客だけでなく、ライティングまでサポートできるのがOHACOの強みです。
まずは、具体的にどんなサポートができるのかをきちんとお伝えしたいので、こちらのページからお気軽にお問い合わせください。

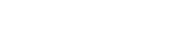
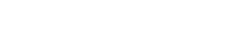
コメント